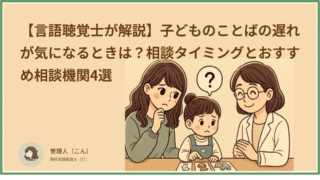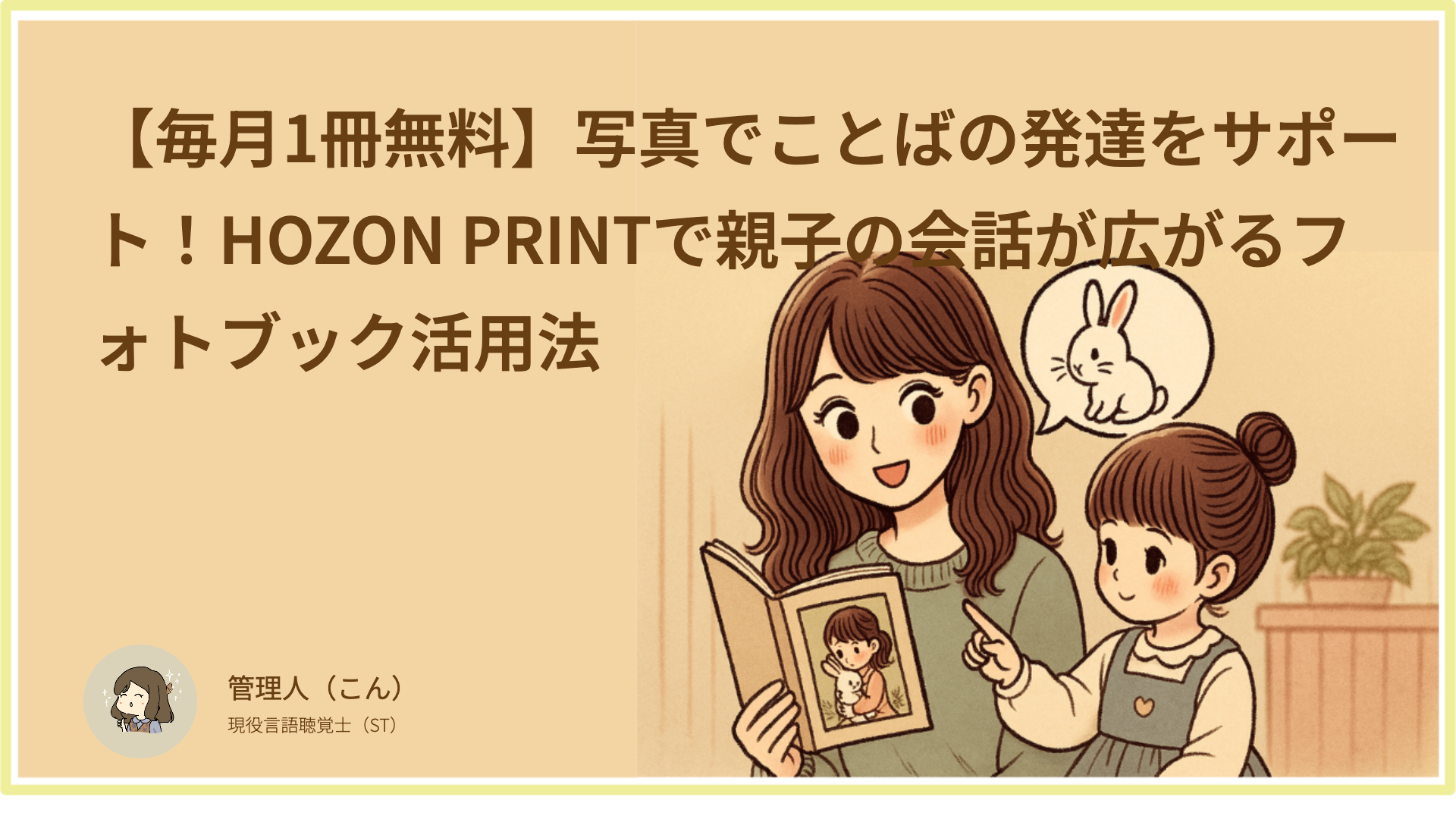2歳でまだ話さない…いつまで様子を見るべき?【言語聴覚士が解説】

「うちの子、もう2歳なのにほとんど話さない…」
2歳なのに、まだほとんどしゃべらない…。大丈夫かな?
そんな不安を感じている保護者の方は、実は少なくありません。
ことばの発達には個人差があるとはいえ、「いつまで様子を見ればいい?」「相談のタイミングは?」と迷いますよね。
この記事では、小児専門の言語聴覚士が以下のポイントを分かりやすく解説します。
- ✅ 2歳の言語発達の目安
- ✅ 様子を見てよいケース・相談すべきケース
- ✅ 家庭でできることばのサポート方法

もう2歳を過ぎたのに、まだほとんど話してくれない!どうすればいいかしら?

それは心配ですね。現状の確認と今後の対応について詳しく解説しますね
2歳の言語発達の目安とは?
2歳ごろの子どもには、一般的に次のような言語発達が見られます。
- 🗣️ 単語の使用:「ママ」「ワンワン」など、10〜50語程度を話す
- 🗣️ 2語文の出現:「パパ きた」「お水 ちょうだい」など、2つの単語を組み合わせて話す
- 🗣️ 理解力の発達:「お外行くよ」「お風呂入るよ」などの簡単な指示が理解できる
⚠️ すべてのお子さんがこの目安通りに発達するわけではありません。
発達にはかなりの個人差があります。
いつまで様子を見てよい?
以下のような様子があれば、もう少し様子を見ながら家庭での関わりを続けてみてもよいでしょう。
- ✔️ 言葉は少ないが、ジェスチャーや指差しで意思表示をしている
ことばでなくても、ジェスチャーや指差しで相手とコミュニケーションできることは、今後、ことばが伸びていく土台ができていることを示しています。 - ✔️ 周囲の大人と関わろうとする姿勢がある
大人と一緒に遊んだり、楽しいね、嬉しいね、と共感し合える、こうしてほしい、ああしてほしいとことばでなくても大人に示している場合は、気持ちの育ちととも今後ことばが伸びていく土台ができていることを示しています。 - ✔️ 日常的な指示を理解している
私達言語聴覚士は、しゃべることばの数ではなく、ことばの理解力を基準に、ことばの発達を見ています。しゃべれるようになるためには、相当の理解力必要となります。
このような場合、今はまだことばで表現できなくても、ことばの土台が育ってきている証拠です。
💡 ただし、3歳を過ぎてもことばの変化が見られない場合は、早めに相談しましょう。
こんなときは専門機関へ相談を!
次のようなサインがある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
- 🚨 2歳を過ぎても単語がほとんど出ない
- 🚨 声かけにあまり反応しない
- 🚨 指差しやジェスチャーがほとんど見られない
- 🚨 意味のあることばが出ず、喃語(なんご)のまま
- 🚨 遊び方や対人関係にも気になる点がある
相談先は以下がおすすめです。
- 🏥 お住まいの保健センター
- 🩺 かかりつけの小児科
- 👩⚕️ 言語聴覚士や心理士などがいる発達相談機関
おすすめは、保健師さんのいる保健センターです。
たくさんのお子さんを見てきているので、お子さんの状態を適切に見てくれます。
また、地域の病院や発達支援機関等の情報を持っています。
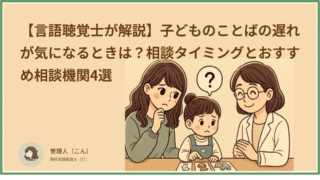
家庭でできる!ことばのサポート3選
興味に合わせて声かけをしよう!
ことばが遅いお子さんには、ことばのシャワーを!と聞くことがあるかもしれませんが、何でも伝えればいいわけではありません。
お子さんが見ているもの、感じていることをママパパがことばで代弁してみましょう。
例:
「くるまブーンだね!」「パパ行っちゃったね〜」「スープおいしいね〜」
❌「これはなに?」と質問攻めにしないのがポイントです。
✔️ 共感しながら話しかけることで、ことばが増えやすくなります。
絵本を読む
絵本は、語彙を広げるだけでなく、やりとりのきっかけにもなります。
おすすめの絵本の読み方
- お子さんが指さしたものをママパパが命名していく
- 「〇〇はどーれ?」とクイズ形式にして楽しむ
📌 絵本に興味がない場合は、無理に読まなくてOK!お子さんの好きな遊びに付き合いながら、ことばのきっかけを作りましょう。
ジェスチャーを積極的に使おう
「おいしい(ほっぺを押さえる)」「くるま(ハンドルを回す動き)」など、簡単なジェスチャーを日常に取り入れてみましょう。お子さんが好きな食べ物や遊びのジェスチャーを取り入れることがお勧めです。
例)アイス:棒アイスを持って舐めるジャスチャー
飲みたい:コップを持った手を口にあてるジェスチャー
💬 「ジェスチャーを教えると話さなくなるのでは…」と心配される方もいますが、逆です!
🗣️ ジェスチャーをたくさん使えるようになると、おしゃべりにもつながりやすくなります。
【まとめ】2歳でまだ話さない…どうしたらいい?
- ✔️ ことば以外のコミュニケーションができれば、しばらく様子を見てもOK
- ✔️ 理解力があり、人と関わろうとしていることが重要
- ⚠️ 3歳を過ぎても変化がなければ専門機関へ相談を
- 🏠 声かけ・絵本・ジェスチャーでことばの発達をサポートしよう!
「うちの子、大丈夫かな?」と不安なときは、ひとりで悩まず、相談先に話してみてくださいね。
きっと、ママパパの不安や心配が軽くなると思います。