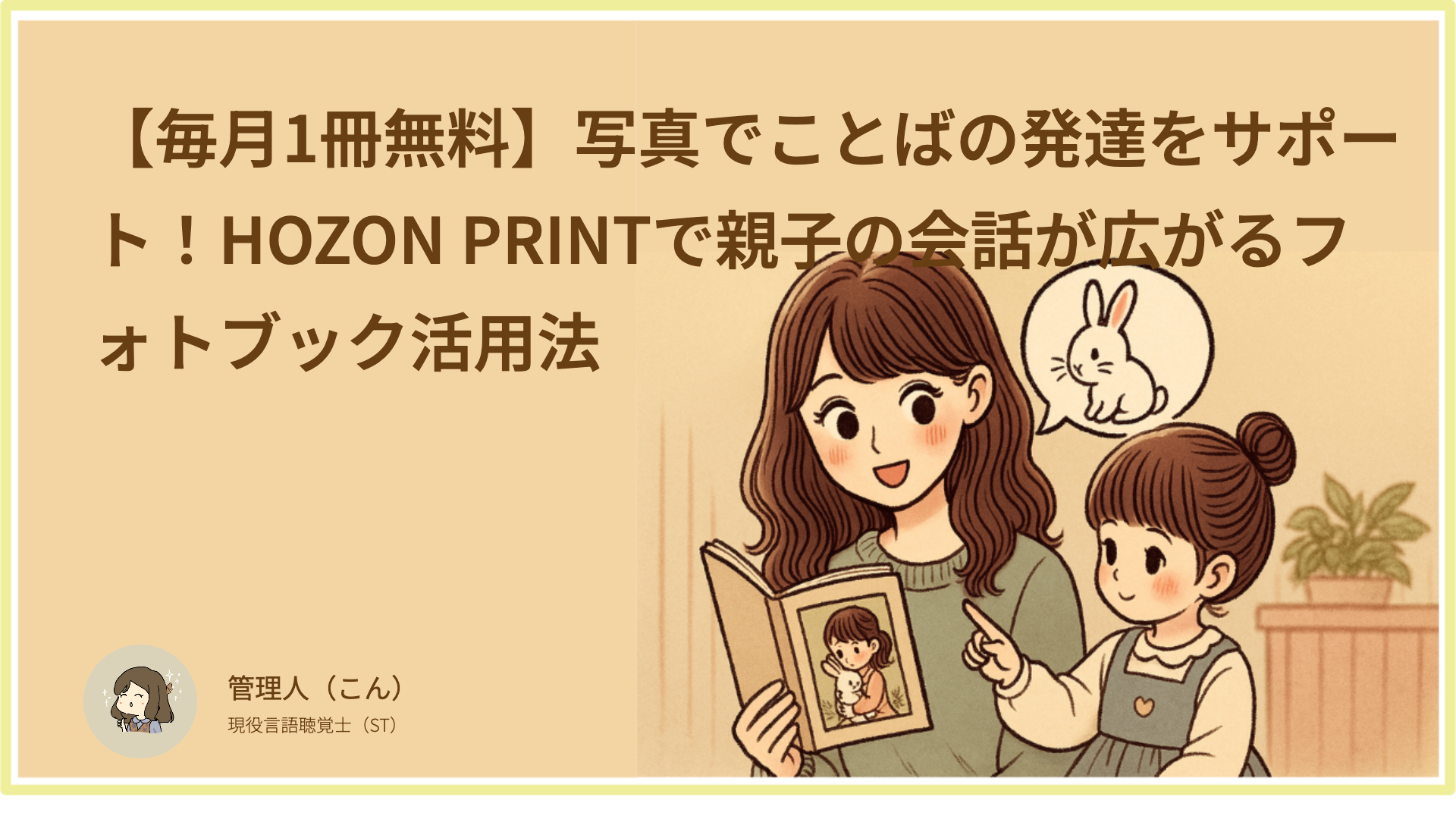【3、4、5歳】親子で楽しむ!ことばの発達を促すことばあそび5選!言語聴覚士が解説

「うちの子、言葉がちょっと遅いかも…」「何をしたら言葉が増えるの?」と悩んでいませんか?
ことばの発達には、家庭での関わりがとても大切です。中でも“ことば遊び”は、楽しみながら自然に語彙や表現力を伸ばせる最強の方法。本記事では、【言語聴覚士が選んだ】おすすめのことば遊び5選をご紹介します!

うちの子、幼稚園に行き始めたけど、少しことばが遅いみたい。ことばの発達を促すのに何かいい遊びはないかしら?

「なぞなぞ」「かるた」など親子で楽しめることば遊びがオススメです。その理由と実践方法について、具体的に説明しますね。
ことば遊びとは?
ことば遊びの定義
ことば遊びとは、言葉を使って楽しむ遊びの総称で、リズムや意味するものの面白さを通じて語彙力(ことばの数)や表現力を育んでいきます。ルールがシンプルで子どもが自発的・能動的に楽しむことができ、遊びを通じて、子どもはことばのリズムや意味のつながりを自然に学ぶことができます。
ことば遊びの種類(韻を踏む遊び、しりとり、なぞなぞなど)
ことば遊びにはさまざまな種類があります。
・「韻を踏む遊び」は、言葉の響きを楽しみながら発音を学ぶのに適しています。
・「しりとり」は、言葉のつながりを考える力を育みます。
・「なぞなぞ」は、言葉の意味や文脈を 理解する能力を鍛えるのに役立ちます。
これらを適宜取り入れることで、子どものことばの発達を総合的にサポートできます。
ことば遊びの効果とは?
語彙力の向上
ことば遊びを通じて、新しい単語に触れる機会が増えます。しりとりやなぞなぞを繰り返すことで、自然に語彙が増えていきます。特に、知らない言葉に出会った際に、意味を考えたり聞いたりすることで、語彙力が向上します。
表現力や想像力を育む
ことば遊びでは、単語を組み合わせて新しい表現を作る機会が多くあります。例えば、リズム遊びや韻を踏む遊びを取り入れることで、ことばの使い方を学ぶだけでなく、創造力を働かせながら自由に表現する力が養われます。こうした経験は、後の作文や会話のスキル向上にもつながります。
コミュニケーション力の向上
ことば遊びは、親子や友達と一緒に楽しむことで、会話のキャッチボールを学ぶ機会にもなります。自分の考えを言葉にする練習になり、相手の言葉を聞いて理解する力も養われます。このように、ことば遊びを通じて、子どもは自然とコミュニケーション力を高めることができるのです。
親子で楽しむ!おすすめのことば遊び5選
仲間あつめ遊び
なぞなぞ遊びができるようになる前の段階でおすすめなのが、この「仲間あつめ遊び」です。特定のカテゴリーのことばを順番に言っていくことば遊びです。
例)・「赤いもの」を順番に言う
・「丸いもの」を順番に言う
・「動物の仲間」を順番に言う
・「あ」のつくことばを順番に言う、などなど
お子さんがうまく言えないときは、時期をずらすか、ヒントをあげてみましょう。また、絵カードの中から選んでもらうのもオススメです。
この仲間集めがスムーズにできると、次に紹介するなぞなぞ遊びが楽しめるようになりますよ。


ポイント!「仲間集め遊び」をすることは、お子さんの頭の中のことばの辞書が整理されるということ。ことばの概念形成も促進されるとってもいいことば遊びです。
なぞなぞ遊び
この時期のなぞなぞは、一般的に言うとんち系のものではなく、物の用途や特徴を出題するクイズです。お子さんが物の名前を知るだけでなく、用途や特徴などの概念を理解し広げていくことができます。
例) ・鼻の長い動物はなーんだ?
・カーカーって鳴く鳥はなーんだ?
・赤くて丸い果物ってなーんだ?
・白い飲み物はなーんだ?
まずは、ママパパが出題することから始めます。
お子さんが知っている、言える言葉のなぞなぞを出しましょう。
お子さんが答えられない時は以下の対応をしてください。
・ジェスチャーでヒントを示す
・最初のことばを教えてあげる(最初に「か」がつく鳥だよ)
特に始めは、どんどんヒントを出してあげましょう。
お子さんが楽に楽しく答えられることが何より大切です。
お子さん自身が、なぞなぞ遊びって楽しい!もっとやりたい!という気持ちに向けていきましょう。
注目!お子さんがうまく答えられなくても絶対に怒らないようにしましょう。なぞなぞ遊びが嫌いになってしまいます。

ポイント!親子で楽しむことが何より大事です。なぞなぞ遊びが親子の楽しい時間になりますように。
しりとり遊び
しりとり遊びが楽しめる前提として、「あ」のつくことば、などが分かる力が必要です。「あ」のつく仲間集めなどを十分に行った後、しりとり遊びに進みましょう。
例えば、「りんご → ごりら → らっぱ」のように言葉をつなげていきます。いつも同じことばの流れにならないように、ママパパの順番でバリエーションをつけましょう。
しりとりカードゲームを使うと、視覚的にも楽しめます。
しりとり遊びができるようになると、単語を音に分解できる力がついているので、文字学習もやりやすくなりますよ。
下記のようなしりとりカードや絵本を使うと、ことばの音だけでなく目で見て楽しめるので、文字の読み学習につながるのでおすすめです。
さかさことば遊び
しりとり遊びができるようになったら、さかさこことば遊びを楽しみましょう。
さかさことば遊びは、例えば「あり」を反対からいうと「りあ」という、さかさから言ってみることば遊びです。
ひらがなで書いたときに2文字から始めて、だんだんと4文字、5文字の単語に進んでいきます。
自分の名前を反対から言ってみる、ママの名前やパパの名前を使うのも楽しいです。
「とまと」「しんぶんし」など、反対から言ってもおなじことばがあることに気づき、面白さを共有しましょう。
文字が読めるようになる頃に、楽しめることば遊びです。
かるた遊び
かるた遊びは、文字が少し読めるようになってきた頃に楽しめる遊びですが、ことばの発達に必要な「聞く力」を育てられるとてもよい遊びです。
特にお正月頃になるとたくさんのかるたが書店などに並ぶので、お子さんの好きなキャラクターや動物、乗り物など、お子さんが楽しめるものを購入し、繰り返し楽しむことをおすすめします。
読み札を聞いてカードを取るだけでなく、読み札の文字の形と取り札の文字の形合わせゲームとする、などいろいろなバリエーションをつくり、何度も親子で楽しめます。
遊び始めの頃は、絵カードのことばの最初の文字が読み札の最初の文字とになっているものを選びましょう。

ことば遊びを効果的にする3つのコツ
子どもの興味に合わせた遊びを選ぶ
子どもが楽しんでこそ、ことば遊びの効果が最大限に発揮されます。好きなキャラクターやお子さんの興味に関連した単語(ことば)を使いましょう。
日常生活にことば遊びを取り入れよう!
遊びの時間を特別に設けなくても、日常の会話の中でことば遊びを取り入れてみましょう。移動の車内やお風呂、買い物時がおすすめです。
間違いを否定せず、楽しく続ける
ことば遊びは、正解を求めるものではなく、親子で一緒に楽しみましょう。子どもが間違えても否定せず、「面白い答えだね!」と肯定的に受け止め、安心して発言できる環境を作りましょう。
まとめ
ことば遊びは、子どもの語彙力や表現力、コミュニケーション力を自然に育んでいくことができる素晴らしい遊びです。日常生活に取り入れることで、楽しく無理なく行うことができ、親子の絆も深まります。
ぜひ今日から「なぞなぞ」や「しりとり」「かるた」などのことば遊びを通して、お子さんのことばの発達を促してみましょう!
親子で楽しみながら、ことばの発達を育むことば遊び。今日からぜひ試してみてください!
よくある質問(FAQ)
Q1. ことば遊びは何歳から始められますか?
A. ことば遊びは0歳からでも始められます。赤ちゃん向けには、オノマトペを使った遊びや手遊び歌が効果的です。本格的なことば遊びは3歳ぐらい〜ですね。
Q2. ことば遊びが苦手な子どもでも楽しめますか?
A. 遊び方を工夫すれば大丈夫です。例えば、オノマトペや手遊びなどリズム感のある遊びから始めることで、徐々に楽しめるようになります。別記事で紹介しています。
Q3. 忙しくてもことば遊びを取り入れる方法はありますか?
A. 登園時や買い物中に簡単なしりとりをしたり、お風呂でなぞなぞ遊びをしたり、寝る前の5分間だけことば遊びを取り入れるのもおすすめです。Q4. ことば遊びの効果はいつ頃から見られますか?
A. 個人差はありますが、続けることで語彙力や表現力が徐々に向上し、会話の幅が広がっていきます。
Q5. ことば遊びは兄弟や友達ともできますか?
A. もちろんです!複数人で遊ぶことで、会話のやりとりが増え、さらにことばの発達を促せます。